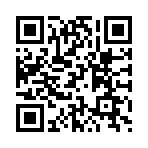2021年05月27日
いいとこどりしよう

本来、日本人というのは江戸時代以来の心学の影響で、自分を高めるということに熱心なんですよ。
心学というのは、神道であろうが儒教であろうが仏教であろうが、いいところがあればそれを取り入れて自分を磨くために役立てましょうという考え方です。
これは日本の思想の非常にユニークなところで、心というものがあって、その心とは玉みたいなものだと考えるのです。
そして、その玉を磨く「磨き砂」は、儒教を使ってもいいし、神道を使ってもいいし、仏教をつかってもいいじゃないか、と。
要するに、心が磨ければ何でもいいというわけです。
これはすごい発想で、いかなる外国の宗教にもない。
たとえば仏教なら仏様の道でしょう。
神道なら神様、儒教なら孔子様、キリスト教ならキリスト様、イスラム教ならマホメット様ですね。
その教えはバラバラでお互いに矛盾しているかもしれないけれど、皆、いいことをいっている。
これを玉のほうから見れば、ああ、役に立つなら何を使って磨いてもいいじゃないか、ということになる。
こういうい発想が日本人にはある。
これは人間学の基礎でもありますね。
by『生き方の流儀』(渡部昇一&米長邦雄)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
要はなんでもいいものを取り入れよう!
ってことで解釈しました。
もともと日本は資源の乏しい国。
古来より渡来した文化をうまく取り入れ
さらに発展させ
独自のものに改良してきたと社会で教わった。
和太鼓もそう。
鼓鐵もそう。
太鼓だけにとどまらず
色んな音楽の要素を取り入れたり
体を使った表現をする和太鼓なので、スポーツの要素を取り入れたり
昔からあるもの
今うまれたもの
様々に取り入れていく。
いいものをいいものにして。
それを鼓鐵の良さに昇華することを目指して。
雑種といえば雑種。
ハイブリッドといえば、言い方かっこいいよね。
混合したもの、ミックスされているもの
でもカオスではない。
エッセンスがどこそこに散りばめられている。
それは計算してそうなっているものと
鼓鐵の自分たちでさえ認識していないうちに取り入れているもの。
なかには言われてもよくわからないものも含め。
そうやってアンテナに引っかかったものをうまく取り入れる。
それも能力のひとつだと思うので、
今後も磨いていけたらと思います。
Posted by
和太鼓集団鼓鐵
at
12:18
│Comments(0)
2021年05月27日
「ミニ」

通常、コンサートやライブは2時間程度で行われるのが一般的かな。
長いと3時間近いのもあるかもしれませんが、
休憩時間をどれくらいとるかの関係もあるかもしれませんが、
和太鼓の場合、だいたい2時間が主流かな。
2時間のプログラムを考えるとなるとけっこう計算が必要になります。
そこで、少し気楽な感じでやれるライブ、
やる側も見る側も。
といっても演奏は手を抜きませんよ。
ガッツリ本気です。
とっかかりの気楽さの話ね。
で、気楽さを考えたときに「ミニ」。
サイズを半分にして1時間のミニライブ。
これだと企画しやすいよね。
今回、鼓鐵が演奏した(あくまで講習会ですが)1時間の枠。
これをヒントに来年夏、この場所で、印岐志呂太鼓のみんなにミニ演奏会を作ってもらおうと思ってます。
バックアップする僕自身も楽しみにしています。
Posted by
和太鼓集団鼓鐵
at
12:16
│Comments(0)
2021年05月26日
ちがうバージョン

以前、印岐志呂太鼓では「青空」を演奏していました。
この「青空」は鼓鐵のバージョンではなく、純に許可をもらって印岐志呂太鼓用にアレンジしたものです。
あっ、とんとこでやってる「青空」も同じバージョンです。
記憶では先に印岐志呂太鼓からやったと思います。
印岐志呂でうまくいったからとんとこでもやり出したような、、、、
まあ、かつて印岐志呂太鼓の子供たちがやってたのですが、
今回お見せしたのは鼓鐵バージョンの「青空」。
あえてセトリに「青空」を入れました。
それは同じ曲でもアレンジ変えるとこんなにちがうんだ!
というのを感じて欲しかった。
で、アレンジ変わって印象がちがうけど、確かに曲は「青空」だなぁ、
というのを感じて欲しかった。
このアレンジの妙。
これも音楽の面白さ。
和太鼓の面白さ。
ですね。
追伸、写真は「青空」じゃなく「回転木馬」です。
気づいた方おられました?
「青空」の写真がなかった(^^)
Posted by
和太鼓集団鼓鐵
at
20:20
│Comments(0)
2021年05月26日
チャッパ

楽器紹介では鳴り物も説明しました。
太鼓ではない、鳴り物と総称している楽器たち。
あたり鉦、すず、そしてチャッパ。
小さいシンバル。
このシンバルからいくつかの鳴らし方によって音のバリエーションが広がる。
和太鼓にはかかせない楽器のひとつ。
太鼓を知っている人にはご存知の楽器ですね。
印岐志呂太鼓にはないチャッパ、
どういうふうな感想を持ったでしょうか?
Posted by
和太鼓集団鼓鐵
at
20:01
│Comments(0)
2021年05月26日
人生はいつたのしいか

花はなぜうつくしいか
ひとすじの気持ちで咲いているからだ
本当にうつくしい姿
それはひとすじに流れたものだ
川のようなものだ
人生はいつたのしいか
気持ちがひとつになり切った時だ
by 八木重吉(詩人)
気持ちがひとつになり切った時。
それを一人だけでなく
みんなでひとつになった時。
常にそれを目指しているのだと思います。
Posted by
和太鼓集団鼓鐵
at
09:19
│Comments(0)